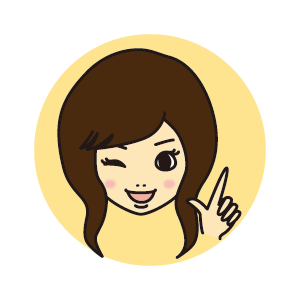新生活がスタートし、慣れない環境にストレスを感じている人も多いでしょう。
連休が終わり、学校や会社が始まるとなんとなく優津な気持ちになる人は少なくありません。
連休明けも元気で健やかに過ごせるよう、食生活から整えていきましょう。
そこで、ゴールデンウィーク後になりやすい5月病の特徴や、5月病対策に効果的な食べ物についてご紹介していきます。
目次
5月病とはどんな症状?

5月病という言葉を聞いたことがあっても、詳しい症状まで知っている人はそれほど多くありません。
何となくだるさが続いていると安易に考えてしまいがちですが、5月病には様々な症状があります。

新生活のスタートとなる4月は慣れない環境に加えて、たくさん覚える必要のある勉強や仕事により、ストレスが溜まりやすい時期です。

その結果、体調が悪くなるのですが、遅れや迷惑をかけたくないという感情があり、仕事や学校を休まず無理をしてしまう人が多くなります。
そして、入学や入社をして1ヶ月後にゴールデンウィークが訪れます。
長い休みによって張り詰めていた緊張感が切れ、脱力したような状態になることで、精神的にも体力的にも様々な意欲が低下してしいます。

ゴールデンウィーク後にはまた学校や仕事が始まりますが、緊張が解れ切った状態なので今までできていたことができなくなることがあります。
・ミスをしやすい
・イライラしやすい
・やる気が無くなる
上記のような様々な症状を引き起こしてしまうのです。

5月病は正式な病名ではなく、適応障害なとど診断されることもあります。
新社会人や新入学生だけが発症する病気ではなく、どの世代にもリスクは十分にあります。
5月だけではなくどの月にも起こりうるので注意が必要でしょう。
5月病は予防できる?

新しい環境にいれば、頭がパンクしそうになるため、ストレス発散にまで手が回らない可能性もあります。
5月病を予防するためにはストレスを溜めないことが最も重要です。

休める時には仕事や勉強のことは忘れてリラックス、リフレッシュすることを心掛けましょう。
自分の好きなことをする時間を作ることで、ストレス発散ができるでしょう。

仕事以外で没頭する時間もリフレッシュになるので、パズルやプラモデルを作るだけでも予防になります。
また、友人や職場の仲間、家族など、気を許せる人に相談することもストレス解消には有効的です。
悩みや愚痴を言うだけでもリフレッシュできますし、笑い話をするだけでもストレスを溜めにくくなるでしょう。
5月病には脳内物質が関わっている!

5月病には「ドパミン」「ノルアドレナリン」「セロトニン」といった3つの脳内物質が関係しています。
ドパミン

ノルアドレナリン

セロトニン

精神安定に関わる物質で幸せホルモンとも言われています。
そうなると、ネガティブな感情が全面に出て鬱のような状態になってしまう可能性もあります。
5月病になったかも…そんな時にはこの食材!

牛乳やチーズ、ヨーグル
・大豆製品
きなこや豆腐、豆乳や納豆
・魚卵
たらこやすじこ、かずのこ
・魚
鮭やブリ、マグロ、カツオ、イワシ
豚肉や牛肉、鶏肉、レバー
・野菜
ブロッコリーやホウレンソウ、枝豆、ニラ
・ナッツ
胡麻やクルミ、アーモンド、ピーナッツ
・果物
アボカドやバナナ、キウイフルーツ
ビタミンB6

炭水化物


噛むことも大切

セロトニンを分泌させるためには「噛む」ことも重要です。
普段噛むことを意識してご飯を食べている人は少ないでしょう。

ヨーグルトや牛乳などの乳製品を摂取することも重要ですが、噛む行為を引き出すためには、プラスして固形物を摂取することがポイントです。
ヨーグルトの中にバナナやキウイフルーツを入れる、大きめに切った野菜をふんだんに入れたミルクスープを作るなど、料理の仕方にもこだわってみましょう。

ナッツ類にいたっては食べて飲み込むまでに多く咀嚼するため、サラダの上にのせる、スイーツに取り入れるなど、積極的に使用してみてください。
また、パンを食べる時には食パンやロールパンよりもフランスパンを選ぶなど、同じ食べ物でも噛み応えのある食べ物を選んでみましょう。
朝ご飯も重要!

セロトニンの働きを良くするためには脳を活性化させることも重要です。
目覚めた時からセロトニンの分泌を促し、1日を順調に乗り切るためにも朝ご飯はしっかりと食べましょう。

朝は食欲がない人もいますが、少しでも口に入れることで脳の活性につながります。
牛乳を飲む、バナナを食べる、スープを飲むだけでも良いので、朝ご飯を食べる習慣を身に付けていきましょう。

ストレスが極限まで溜まり、精神的に辛い状況であれば食事を改善することで、徐々に状況が変化してくるでしょう。
精神的に不調であると、何事にもやる気が無くなり食生活も不規則になりがちですが、摂取する食材を意識するだけでセロトニンが分泌され改善が見込めます。
バランスの良い食事を心掛け、趣味に没頭してリフレッシュするなど、ストレス発散を行うなどして5月病とは無縁な生活を手に入れましょう。